【疼く記憶の官能日記】19才、溺れる記憶

別れて半年。時間が経てば忘れられると思っていた。彼の声も、匂いも、肌の感触も、すべてが過去になっていくはずだった。
でも――それは、甘い幻想だったのかもしれない。
ふとした瞬間、あの人を思い出す。電車の中、ベッドの上、シャワーの最中。些細な仕草や言葉が記憶の底から蘇るたび、心だけでなく、身体の奥まで熱くなる。まるで、彼がまだそこにいるみたいに。
触れてほしいと願う指先。名前を呼びたくなる唇。求めるたびに疼く、胸の奥と秘めた場所。
――忘れられない。忘れたくても、忘れられない。
私は、彼の記憶に溺れている。
刻まれた温度
雨の音が窓を叩く夜。薄暗い部屋の中で、私はひとり、ぼんやりとスマホを見つめていた。
彼の名前を呼ぶことはもうない。けれど、検索履歴にはまだ彼の名前が残っている。消すこともできず、新しく上書きすることもできず、ただそこにあるだけの名前。それが、私の未練の証なのだと分かっていた。
ため息をついてスマホを伏せる。けれど、目を閉じれば浮かんでくるのは彼の顔。
「……っ」
思い出したくないのに。忘れたいのに。
それなのに、身体が覚えている。彼の手の温度、抱き寄せられたときの感触。ベッドの上で何度も求め合った夜のこと。彼が私の名前を囁きながら、指で、唇で、舌で私を侵していく感覚。
頭の奥がじんじんと熱を持ち、太腿の内側がじわりと濡れていくのが分かった。
――ダメだ。
自分に言い聞かせるように、シーツを握りしめる。
でも、どうしようもなかった。
記憶の中の彼は、今も私を求めている。
指先に残る幻影
夜が更けるほどに、私の中の渇望は増していった。
ベッドに横たわりながら、そっと腿を擦り合わせる。指先が肌に触れるたび、彼が触れていた感覚が蘇る。あの熱い吐息、低く響く声。耳元にかかる彼の息遣いを思い出すだけで、奥が疼いた。
「……んっ……」
自分で触れるなんて惨めだと思うのに、もう止められない。そっと下着の上から指を滑らせる。薄布越しに感じる湿り気に、羞恥と興奮がないまぜになる。
もし、今ここに彼がいたら。
その想像だけで、全身が甘く震えた。
夢中で指を動かす。頭の中には、彼しかいない。囁く声も、荒い息も、深く貫かれる感覚も、すべてが鮮明に蘇る。
「……あ……っ、やだ……」
耐えきれず、声が漏れる。
身体が勝手に、彼を求めてしまう。
記憶の中の彼に抱かれながら、私はひとり、果てた。
熱に抗って
朝になっても、昨夜の余韻が身体の奥に残っていた。
ベッドの上で伸びをする。肌に触れるシーツがひどく冷たく感じられた。心も、同じだった。
彼の記憶に溺れるたび、求めるたび、私はひとりで燃え尽きる。満たされるどころか、むしろ空っぽになっていく気がした。
――こんなふうに、いつまで彼を引きずるつもりなのだろう。
虚しさを振り払うように、スマホを手に取る。
LINEのトーク画面を開く。そこには半年間、動くことのなかった彼の名前がある。指が震える。
「久しぶり。元気?」
打ち込んでみる。たったそれだけの言葉なのに、送り出すのが怖かった。
(……送るべき? それとも、このまま……)
迷いながら、指を画面の上に置く。けれど、そのまま動けなかった。
思い出すのは、別れた日のこと。あのとき私たちは、確かに終わったのだ。どんなに身体が彼を覚えていても、心が渇望しても、彼はもう私のものではない。
「……ダメだよね」
小さく息を吐いて、ゆっくりと打ち込んだ文字を削除する。トーク画面を閉じると、スマホを伏せて、ぎゅっと目を閉じた。
渇望は簡単には消えない。それでも、私は過去に戻ることはできない。
――この熱に抗って、生きていくしかない。








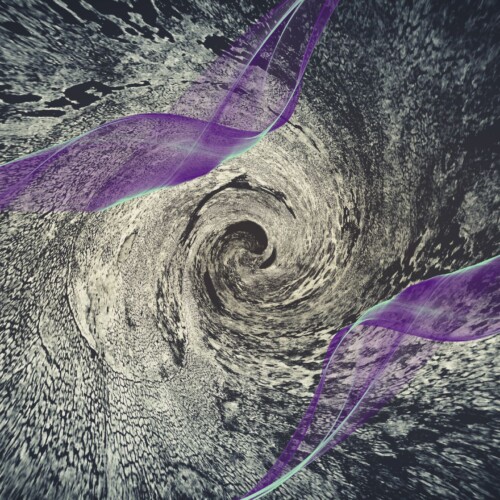




この記事へのコメントはありません。