【妄想官能物語】背徳の甘い罠 1-2 秘めたる動揺

第一章「偶然か、必然か」
第二章「秘めたる動揺」
「……少しだけ、なら。」
その言葉を口にした瞬間、喉が乾いた。
翔は微笑みながら、店の奥にあるボックス席へ私を促した。逃げるように席を立ったはずなのに、気づけば彼の隣に座っている。ふたつ並んだグラスの間に、緊張が流れ込んだようだった。
「久しぶりに会ったんだから、もう少し話してもいいだろ?」
そう言う彼の声は、昔と変わらず穏やかで、けれどどこか試すような響きを持っていた。
「……うん。」
うなずきながら、私はワインを口に運んだ。ほんのりとした甘みが喉を滑り、身体の奥へと溶けていく。その感覚が、記憶の扉を開けた。
8年前、大学時代。
私たちはいつも、こんなふうに飲んでいた。カウンター席よりも、どこか閉ざされた空間の方が落ち着いた。翔は、少し強いお酒を好んでいた。私はそれを真似して、無理をして背伸びしていた。彼に大人びた自分を見せたくて。
「お前、酔うとすぐ顔赤くなるよな。」
そう言って笑いながら、翔はいつも私の髪をくしゃりと撫でた。
――そんな記憶が、鮮明に蘇る。
まるで、時間が巻き戻ったみたい。
でも違う。あの頃の私には、夫はいなかった。罪悪感なんて、何もなかった。
「由梨?」
翔の声に、はっと意識を戻した。
「……ごめん、なんでもない。」
彼は静かにグラスを傾けながら、私をじっと見つめていた。その視線に射抜かれたまま、私は居心地の悪さを感じていた。
「由梨は、今幸せか?」
また、その質問。
「……そんなこと、普通聞く?」
「普通は聞かない。でも、俺は由梨のことを知ってるから聞くんだ。」
彼の目は真剣だった。
「私は……」
私は何を言うつもりだったんだろう?
「……うん、幸せだよ。」
口に出した言葉が、妙に空虚に響いた。
翔は苦笑して、グラスを置いた。
「そっか。」
それ以上、彼は何も聞いてこなかった。でも、その「そっか」に、彼の言いたいことが全部詰まっている気がした。
沈黙が流れた。
外では雨が降り始めたらしく、窓ガラスに水滴が流れ落ちている。店内の柔らかいジャズの音が、妙に遠く感じる。
「……もう遅いし、帰らなきゃ。」
私は、逃げるようにそう言った。
「送ろうか?」
「いい、大丈夫。」
「そっか。」
翔はそう言って、再び微笑んだ。でもその笑顔は、少し寂しそうだった。
「じゃあ、またな。」
「……また。」
言葉が喉の奥でつかえる。
私は、何に対して「また」と言ったんだろう。
もう会うつもりはないのに。そうしなきゃいけないのに。
でも、バーを出た後も、彼の視線の熱だけが、肌に残っていた。
➡️ 次章『再燃する記憶-秘めたる動揺』
⬅️ 前章『再燃する記憶-偶然か、必然か』
🏠 小説TOP『求める罪…それでも私は堕ちていく』








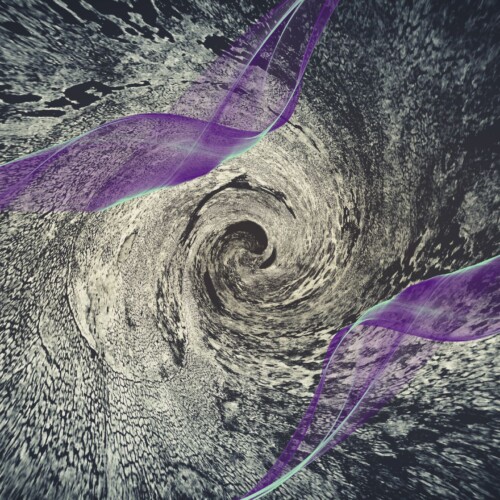





この記事へのコメントはありません。